石工事の施工
石工事を行う際には、複数の施工方法があり主に乾式工法と湿式工法があります。また、外部に使用するのか、内部に使用するのか、取付ける下地面の状況によっても工法が変わります。
乾式工法

モルタルを使わない工法です。下地材にステンレス製の金属金物を使って固定して行きます。この工法は、軽量化、工期短縮、剥離防止、耐震性、耐風圧性などの問題を考慮して開発された工法です。中でも耐震性能を確保する為にロッキング方式とスウェー方式があり、スウェー方式の方がより耐震性に優れますが、取付下地に使用する金物や取付にかかる費用もかなり高くなります。
湿式工法

モルタルを使用する工法です。石材を固定するのに鉄筋を使用しますが、その際の鉄筋には錆止め塗装が必要となります。この工法は戦前に使用していた分厚い石材には適していたのですが、戦後になり薄い石材を使用するようになってからは、熱による石の膨張や反りの問題が多く発生し、その事からモルタルの接着力にも影響を及ぼし、石材が剥落すると言う問題にまで発展し、現在では外壁コンクリート面への石工事において、湿式工法での施工は殆ど行われていません。
外壁面に使用する場合

コンクリート等の壁面にファスナーと呼ばれる金属製の金物で下地を組んで石材を張って行きます。石材自体の強度とファスナーの強度で、石材自体を支えますので、事前に強度計算を行う必要があります。また、施工高さの限度や必要な石厚などを定める基準があり、専門的な検討を要します。
内壁面に使用する場合
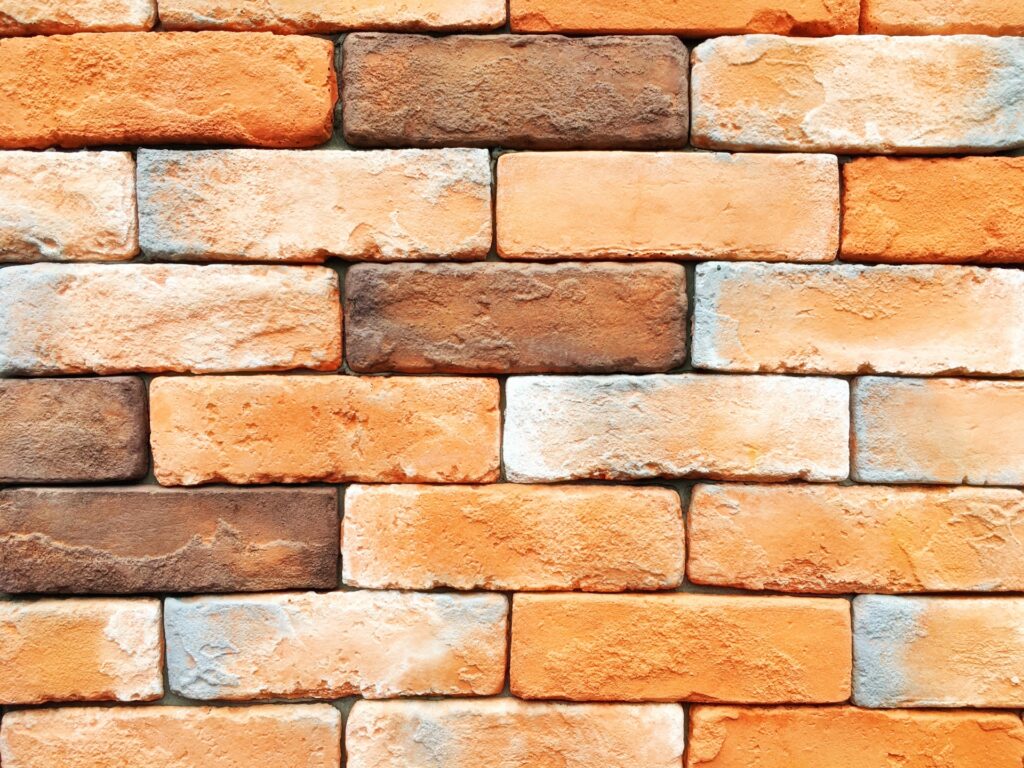
内壁面に使用する場合、石材を張り付ける下地面の状況によって複数の工法があります。内壁面に張る場合は、外壁に張る場合に比べて比較的低い高さの場合が多いですので、板の厚みや取付方法なども基準が少し緩くなりますが、強度計算はしっかり行う事が重要です。
コンクリート下地

空積工法で施工します。下地面のコンクリートに、後から埋め込み施工したアンカーもしくは鉄筋に、ステンレス製の線で石材を結びつけて固定する方法です。石の裏面のステンレス線部分には無収縮モルタルを充填します。施工できる高さは3メートルまでですが、それ以上になる場合は特別な金物を使う必要があります。
鉄骨下地

内部鉄骨乾式工法で施工します。鉄骨の場合、無収縮モルタルを充填出来ない事から、専用の金物で下地を組んで石材を張り付け固定します。外部の乾式工法で使うファスナーは使用しません。施行高さの限度は3メートルで、それ以上になる場合は特別な金物が必要となります。
ボード系下地
ボンド併用簡易金物工法で施行します。専用の接着剤と金物を併用して石材を張り付け固定します。この工法の場合には目地が必要となります。